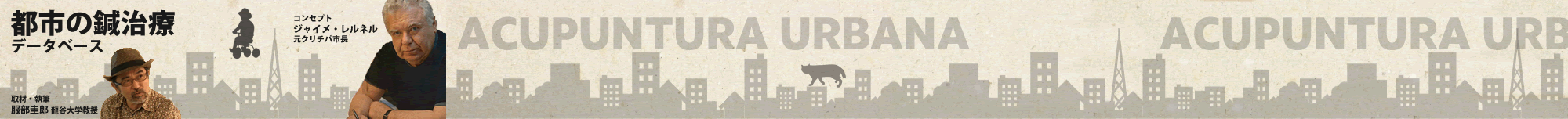302 奄美群島の黒糖焼酎(日本)
302 奄美群島の黒糖焼酎(日本)
ストーリー:
奄美群島は、南西諸島のうち、薩南諸島南部にある島嶼群のことを指す。長さは200キロメートルにおよび、総面積約1,250キロ平方メートル。有人島は奄美大島を始めとして8つほどある。総人口は約10万人である。2021年にそのユニークな生態系、自然を保全するために、その一部の地区が世界自然遺産に登録された。
この奄美群島には、そこでしか造れないお酒がある。それが黒糖焼酎である。それは、その地域のユニークな生態系や、独特な文化・伝統といった風土を反映させており、その地域アイデンティティの象徴のような役割をも果たしている。
奄美群島での焼酎製造の始まりははっきりとは分かっていないが、タイから琉球経由で製法が伝わったと考えられている。1609年に奄美群島は薩摩藩の支配下に置かれるが、その数年後、薩摩藩は奄美に焼酎を貢納する命令を出している。このことより、既にこの頃は蒸留酒である焼酎が造られていたと推察することができる。
ただ、江戸時代を通じて、黒糖は藩の専売品であったため、庶民が使うことは許されず、黒糖焼酎は表向きには製造されていないことになっている。明治時代には沖縄から泡盛の製法が伝わり、自家醸造が行われる。これら自家醸造でつくられたお酒は家庭消費用であった。その後、新政府は酒造を免許制とし、お酒を製造する上では届出と免許料が必要とされたが、それでも自家醸造は続けられていたと言われる。ただ、この頃は、黒糖焼酎はそれほど飲まれてはいなかった。
その後、第二次世界大戦の敗戦によって奄美群島は米政府の統治下となる。本土との貿易が制限され、米が不足したため泡盛がつくれなくなり、黒糖も販売先を失った。そのような状況下、人々は米の代わりに黒糖を用いて酒造りをするようになった。
終戦から八年を経て、奄美群島は日本に復帰することになった。しかし、黒糖を使った蒸留酒は当時の酒税法ではラム酒であり、スピリッツとして分類されてしまう。スピリッツは焼酎よりも約3割も高い税金を課せられる。そこで酒造組合をはじめとした関係者は国税庁に行き、状況を改善することを陳情した。国税庁も、それに対処するために、酒税法の特例通達により、一次仕込みに米麹を使うことを条件に、黒糖を使用した焼酎製造を奄美群島だけに認めたのである。
2023年2月現在、奄美群島には25の製造免許を有する黒糖酒造がある(そのうちの一つは現在、製造していないので実質的には24)。また、共同瓶詰め工場が2社ほどある。人口4,000人に一つの酒造が存在するという計算となる。これらの酒造は、独自の手法で製造しているため、さらに、一つの酒造でも様々な黒糖焼酎をつくっていることもあり、その銘柄の数だけでも170前後となり、度数や容量別などまで考慮すると製品の数は380前後になる。このように、非常にバラエティに富んだ商品ラインナップを奄美群島の黒糖焼酎は提供しているのだ。また、奄美群島では、祝い事などで必ず、黒糖焼酎を飲むという習慣があり、それはそのようなイベントに付随する踊りや民謡といった伝統文化とも強い関係性を持っている。
このように黒糖焼酎は奄美群島といった地域ブランド性を極めて強く有しており、そして奄美の人達も、それで奄美群島の地域経済を活性化させようと積極的に活動している。しかも、その活動は自由度が高く、それぞれの人達が各自の創意工夫をすることによって、ブランド自体の魅力を高めている。
人口減少、グローバル経済の台頭により、地域経済は厳しい状況にあるが、奄美群島のような地域をアイデンティティとするストーリー性のあるお酒を通じて、その地域経済、地域文化、地域アイデンティティ、そして人々の地域への愛着心を強化できることを、奄美群島の黒糖焼酎は示唆している。そこには「お酒」と「地域」との幸せな関係を見ることができる。
キーワード:
地域アイデンティティ
奄美群島の黒糖焼酎の基本情報:
- 国/地域:日本
- 州/県:鹿児島県
- 市町村:奄美市等を含む奄美群島
- 事業主体:25の黒糖焼酎醸造所
- 事業主体の分類:民間
- デザイナー、プランナー:国税庁等
- 開業年:1953
ロケーション:
都市の鍼治療としてのポイント:
黒糖焼酎のどこが「都市の鍼治療」なのか、と言われると一瞬その答えに窮する。それは、都市デザイン的なプロジェクトではないし、空間的な「ツボ」がある訳ではない。空間としての概念はある。ただ、それは奄美群島という巨大な地域である。しかし、それを地球規模での空間マネジメントという視点で捉えると、それは「奄美群島」というツボをものの見事に押さえた、地域アイデンティティを強化するため、そして地域資源によって地域経済を回していくために、極めて高い効果が期待できる取り組みであると考えられる。
黒糖焼酎の魅力に惹かれて、奄美大島で暮らし、その情報を内外に発信しているオーストラリア出身のジョン・カントゥ(John Cantu)氏は、筆者の取材でその魅力を次のように語ってくれた。
「特定なところでしかつくれないアルコール飲料というところが魅力。シャルドネーが特定の葡萄しか使えないという制約下でブランディングに成功したように、奄美群島にしかつくれない黒糖焼酎のブランド価値は高い。この限定性によって、希少価値が生み出される。また、黒糖焼酎がつくられたストーリーのポテンシャルも高い。ストーリー消費が期待できるお酒である。製法も麹を最初から使っているというのは、海外では例をみない。また、ウィスキーなどは何回も蒸留するが、黒糖焼酎は一回の蒸留で飲める。これは、奇跡的なことである。海外にはない日本の技術や創意工夫が多くみられる。当然、お米も使っていて、日本のブランド品としての価値も高い」。
カントゥ氏のこの発言からも、黒糖焼酎のブランド性の高さを改めて確認することができる。日本で黒糖焼酎が製造できるのは奄美群島だけ。この地域限定性がもたらすブランド価値は計りしれない。そして、そのブランド価値を高めるために奄美群島の人達は、奄美群島という決して人口も多くなく、面積的にそれほど大きくもない地域であるにも関わらず、酒造のある場所、その歴史、杜氏の指向などによって多様な黒糖焼酎がつくられているのだ。例えば龍郷町にある山田酒造の「山田川」は、米もサトウキビも100%龍郷町産という銘柄である。原材料が貴重なため、その生産量は年間700本だけという希少なものであるが、そのような銘柄は、その風土性を強力に発現させ、それは他の地域ではつくることが適わないようなオーセンティシティを纏っていくのである。
奄美群島のように、その地域アイデンティティを強烈に発露する商品を見出し、それを用いた地域ブランディングをすることは、地域マーケティング的なアプローチではあるが「都市の鍼治療」的であると考え、ここに事例として挙げさせていただく。
【取材協力】
John Cantu氏(Amami Tours)
富田酒造、町田酒造、奄美大島酒造、奄美市役所紬観光課
【参考文献】
『あまみの甘み あまみの香り』鯨本あつこ、石原みどり、西日本出版社(2016)
類似事例:
046 ギネス・ストアハウス(ギネスビール博物館)
163 サントスの珈琲博物館
183 ドルトムンダーUタワー
277 鶴田商店
301 伝泊
328 バウムクーヘン都市ザルツヴェーデルのヘニッヒ
・八丁味噌、岡崎市(愛知県)
・夕張メロン、夕張市(北海道)
・アイラモルト、アイラ島(スコットランド)
・スコッチ・ウィスキー・エクスペリエンス、エジンバラ(スコットランド)
・アイリッシュ・ウィスキー博物館、ダブリン(アイルランド)
・ダフタウン・ウィスキー博物館、ダフタウン(スコットランド)
・バーボン・エクスペリエンス、ルイビル(ケンタッキー州、アメリカ合衆国)
・サントリー・ウィスキー博物館、北杜市(山梨県)
・ハバナ・クラブ博物館、ハバナ市(キューバ)
・三連水車の保全、朝倉市(福岡県)
・ワイン博物館、ボーヌ(フランス)
・コカコーラ博物館、アトランタ市(ジョージア州、アメリカ合衆国)
・恵比寿ビール記念館、渋谷区(東京都)
・ザ・ハーシー・ストア、ハーシー(ペンシルベニア州、アメリカ合衆国)
・ビア・ウント・オクトーバーフェスト博物館、ミュンヘン市(ドイツ)

 Back
Back