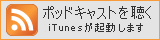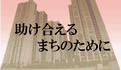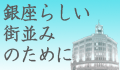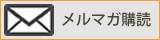2009年02月12日
都市の音風景
■喧騒のメガシティ
前号では図像で表された都市の表象を扱ったが、今回は聴覚による都市の印象についてである。2000年の春に訪れたバングラデシュのダッカの喧騒は今も耳に残っている。この混雑した街を移動するのには、小回りの利く「リキシャ(Rickshaw)」を使うのが便利である。その語源は「人力車」だが、車夫は自転車で引っ張る。少し遠くまで行くには、人力を小さなエンジンに置き換えた三輪のベビータクシーを使う。空港に出迎えてくれた現地の学生とホテルまでこのベビータクシーに乗ったが、小一時間後にホテルに着いた時には喉がヒリヒリであった。小さなエンジンがあえぎながら走る時に吐き出す煙と凄まじい騒音の中での会話(叫び合い)のためである。ダッカ滞在中は、どこに行っても騒音の圧力に圧倒されていた。大小さまざまな車の調整不良エンジンが出す音に加えて、いろいろな音色のクラクション。こんなに頻繁に誰もが鳴らしてあちこちから聞こえたのでは警笛にならないのではと思う。実際に、街を行く人はほとんど無反応である。このクラクション騒音は発展途上国の大都市ならどこでも見られる一般的現象である。そういった国から日本に来た留学生が、多数の車が走る日本の都市の静かさに驚く理由がよくわかる。

あらゆるタイプの騒音源が街を走るバングラデシュの首都ダッカの中心街
■聴覚的ランドマーク
昨年のローマではまったく違った街の音を体験した。それは人とトレビの泉で待ち合わせをした時のことである。近くまで来て見通しがきかない曲りくねった道に迷っていたところ、噴水の音が聞こえ、それに導かれてたどり着くことができたのである。このあたりは細い道の両側に石造の建物が並んでいるので、その壁に音が反射してきたのだろうか。それをたどって行くと徐々に音が大きくなり目的地に接近しているのが実感できた。トレビの泉は遠くから見ることができないが、噴水の音が聴覚的なランドマークとしてその場所を特定するのを助けている。こういった聴覚的なメリハリのある音風景が都市の体験を豊かにしてくれるのだろう。

(写真左)細く見通しのきかない古いローマの街路
(写真中・右)トレビの泉
■東京の音風景
東京はクラクションの騒音は最小限だが、聴覚的なランドマークも思い当たらない。環境庁(現・環境省)が1996年に選定した「日本の音風景100選」には、東京都23区から、「柴又帝釈天界隈と矢切の渡し」が下町ならではの雑踏と江戸川の野鳥の声、朝昼晩の時を告げている上野のお山(寛永寺)の「時の鐘」、石神井公園に近い「三宝寺池の鳥と水と樹々の音」が入っている。しかしこれを日常の中で意識した人はそれほど多くはないだろう。聴覚による情報は、「耳を澄まして」注意を向けて聞こうとしない限り意識に残らない。だから、街の音が場所と結びついて感じられ記憶されるのは、特定のイベントに関連付けられている場合が多い。三社祭りの頃には神輿を担ぐ掛け声や囃子が浅草界隈の街の音になり、また大晦日に近くなると上野のアメ横には売り手の掛け声が連想される。
こういった伝統的な街の音ではなく、人工的に音風景(サウンドスケープ)をデザインしようとする動きがある。蒲田駅の「蒲田行進曲」などの駅メロ、発メロや、ディズニーランドのアプローチでの音楽など、その場所を印象付けたり、高揚感を演出したりするのはいいとしても、公衆トイレなどでBGS(Back Ground Sound)として鳥のさえずりなどをスピーカーで流しているのはいただけない。「鳥のさえずりが聞こえるほど自然が豊かだ」というように、音風景がそこの環境の質(アメニティ)を捉える一つの大切な指標であるのに、それが狂わされて違和感を覚えるからだろう。アメニティの意味は “the right thing in the right place”つまり「しかるべきものがしかるべき場所にあること」と言われるが、都市の音風景についても、正にそう言えるように思う。

(写真左)三社祭りの神輿
(写真中)大晦日のアメ横
(写真右)ディズニーランドのアプローチ
(大野隆造)
- Permalink
- 東京生活ジャーナル
- 13:20
- in 05世界から見た東京