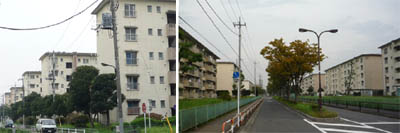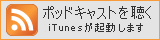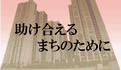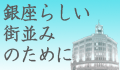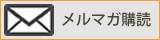2008年10月09日
都市の階段:記憶の拠り所として
■重慶の階段
先月、中国・重慶を訪れる。重慶は北京、上海、天津についで4番目の特別市で、揚子(ヤンツー)江と嘉陵(ジャーリン)江に挟まれた半島状の丘陵都市である。かつての重慶の様子を伝える墨絵には、急な斜面に張り付いた家屋とその間をつなぐ階段が描かれている。この絵は決して誇張ではない。というのも、この街の階段とそれを包む霧のイメージは、26年前にも訪れたことがある私のイメージと重なるからである。

嘉陵江に面する臨江門付近を描いた墨絵と1983年に筆者が撮影した写真
ところが、今回の重慶はその様子が一変していた。交通の障害となる階段は姿を消して、どこにでもある高層ビルと高速道路が作る現代都市の景観を呈していた。河岸側の道路面から建物に入り、エレベータで11階まで昇って外の出ると、崖上の道路面に出る。これはバリアフリーの面からは確かに大きな改善である。また車で行き来できない階段は都市の交通ネットワークを断ち切ってしまう厄介ものには違いない。しかし、一方で重慶の持っていた特異な景観的アイデンティティを喪失したことも事実である。

今日の臨江門付近の模型写真と屹立する高層ビル群の河岸通りからの見上げ
■階段における行為
都市の階段は、人のスムーズな移動を妨げるが、そうであるが故に通常の街路とは違う「場所」として、意識される。またそこでは、段差を利用して腰かけて留まることが出来たり、遠くの眺望が得られたりすることもある。そういった行為が、自分ひとりで、または誰かと共に行われることによって、その場所が特別な場所として記憶され、そこに愛着を込めて名前が付けられたりする。その代表例が、ローマのスペイン階段である。言わずと知れた映画「ローマの休日」で一躍世界的な観光スポットとなった所である。しかしそれほど有名ではなくとも、イタリアには数知れない魅力的な階段が街にある。山が海に迫る港湾都市ジェノバは、宮崎駿が「魔女の宅急便」で描いた街のモデルとも言われているが、そこで見つけた階段はその一例にすぎない。

(写真左・中央)ローマのスペイン階段とその日陰で休む人々
(写真右)ジェノバの階段
では、東京はどうであろうか?実は、東京にも多くの階段がある。「~坂」と呼ばれる中にはスロープだけでなく階段も含まれる。麻布台の雁木坂や湯島の実盛坂などがその例である。武蔵野台地の東端が東京低地と接する都心あたりでは15~25mの高低差を生み、台地は小さな谷に刻まれて様々な方向に下る坂、階段が作られた。湯島あたりでは東に下るが、「夕やけだんだん」という魅力的な名前を持つ谷中銀座に至る階段は西向きで、その名の通り夕焼けが眺められる。松本泰生氏は著書「東京の階段」(日本文芸社、2007)で126もの階段を紹介し、その楽しみ方を語っている。

谷中銀座側から見た「夕やけだんだん」とその名前を記した碑
■外部記憶装置としての階段
人間の記憶は、脳の中にすべて蓄えられているのではなく、生活する環境の中に部分的に埋め込まれている。一度訪れた場所への行き方をあらかじめ思い出せなくても、その途中まで行くとまわりの様子から、どちらに進めば良いかわかることがある。つまり、環境は私たちの記憶を引き出すことを助ける外部記憶装置のようなものである。都市の発展に伴って、建築が建て替えられて様子が変わっても、その地形的な特徴はあまり変わらないため、それによる記憶は保持される。しかし、重慶においては、地形的特徴までも変化し、身体的に体験される階段が姿を消すことによって、記憶を支える基盤が失われていた。イタリアの例で見たように、階段は都市の中で様々な行為と結びついて、記憶の拠り所となる可能性をもっている。東京の階段の現状は、とてもイタリアとは比べられないが、その価値を見直して少し手を加えれば、様々な行為を誘発し、記憶の拠り所となる魅力的な場所にすることができると思う。
(大野隆造)
- Permalink
- 東京生活ジャーナル
- 16:11
- in 05世界から見た東京