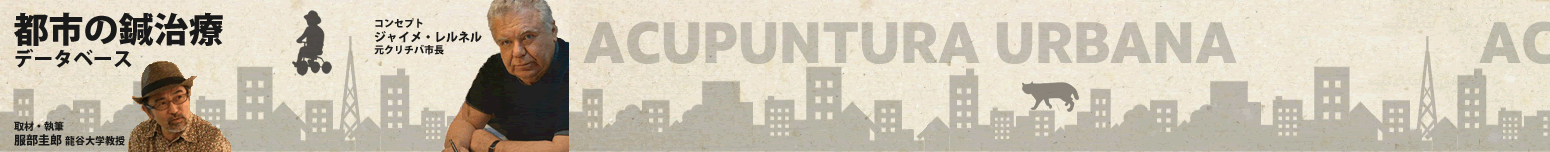平和通買物公園は、北海道の旭川市の駅前にある歩行者専用道路である。旭川市の旭川駅から8条通りまでの1キロメートルほど続く幅20メートルほどの歩行者空間は、日本の都市にはめずらしい歩行者のための広場、公共空間である。
最初に平和通りの車両交通の禁止、路面の自由化の構想を商店街、青年会議所、旭川市で検討したのは1963年であった。その後、1969年に社会実験として道路から自動車を排除させ、その良好な結果を受けて、1972年6月には日本で最初の恒久的歩行者天国となった。これは、銀座の歩行者天国事業を先んじていた。当時の市長であった五十嵐広三氏は、平和通りを歩行者天国化することを市政方針で発表し、その具体化を図ったのである。それは、自動車が我が物顔で行き来する都市空間に対抗して、人がゆったりと買い物が楽しめる緑の空間であり、「人間性回復」をアピールすることが意図された。
誕生時の基本的なコンセプトは次の4つである。
① 道路は本来人間のためにあるという発想
② 都市化の中に人間性を取り戻す空間をつくりだす
③ 市民が主体となったまちづくりである
④ 商店街の近代化であり、また旭川の魅力づくりである
その事業経費は当時のお金で8000万円であったが、2000万円を給付金、残りは旭川市と商店街が折半するなど、行政と市民がまさに協働して実現した事業であった。
ただし、その翌年のオイルショックによって第二次再開発は断念され、それが正式に歩行者専用道路として都市計画決定されるのが1995年。現在、存在する完全なる歩行者専用道路としてリニューアル事業が推進されるのは1997年からで、それが完成したのは2002年である。この時の基本コンセプトは次の3つから構成された。
① 北国の自然が感じられる道づくり
② 人に優しい歩行環境づくり
③ 冬でも快適な買物環境づくり
このリニューアルによって、以下のような左右対称の空間デザインが施され、これらはリニューアル以前に比べてもアメニティを向上させることに成功したと捉えられる。
① 店舗に面した左右幅4メートルは歩道として位置づける(実際は見分けはつけない)。
② さらにその内側の3メートルは「施設帯」として、ここに街路樹や電灯などを配置する。
③ 施設帯の内側の幅6メートルの空間は、造形物は何も置かないようにした。
④ 歩道部分においてはロードヒーティングが設置された。
⑤ 以前あった縁石は取り除かれ、道路空間は平坦性が確保されることになった。
⑥ 電線は共同溝方式によって地中埋設化された。
⑦ 路面は基本、自然石もしくは自然石風の擬石で統一されグレー色を基調とするようにした。
⑧ 照明やストリート・ファーニチャーも人間のスケール感を意識してデザインした。
リニューアルをしても、当初の計画理念であった「人に優しい道路」、「人が主人公である道路」は継承されて、今日に至っている。
これらの空間の維持管理は、旭川市役所の土木管理課と商店街とが協定を結んで、管理の棲み分けをして行っているなど、行政と市民とがともに支え合ってつくられているのが買物公園なのである。
買物公園は、広場的な役割も果たしており、毎年2月には「氷彫刻世界大会」の会場として使われ、6月には大道芸フェスティバルなども行われている。つくられてから40年以上経ち、今でも多くの市民が行き交い、まさに旭川の「顔」として位置づけられ、親しまれてきている。日本の都市ではめずらしく公共性が溢れる空間である。
091 平和通買物公園 (北海道 )







平和通り買物公園は、北海道の旭川市の駅前にある歩行者専用道路である。最初に車両交通の禁止を検討したのは1963年。その後、1969年に社会実験として道路から自動車を排除させ、その良好な結果を受けて、1972年6月には日本で最初の恒久的歩行者天国となった。これは、銀座の歩行者天国事業よりもはやい。
平和通買物公園 の基本情報
- 都道府県
- 北海道
- 州/県
- 北海道
- 市町村
- 旭川市
- 事業主体
- 旭川市、旭川平和通商店街振興組合
- 事業主体の分類
- 自治体 市民団体
- デザイナー、プランナー
- 五十嵐広三
- 開業年
- 1972年、1997年(リニューアル)
ストーリー
地図
都市の鍼治療としてのポイント
この買物公園が社会実験で具体化された時に、ある小学生がつくった詩がある。
「夏休みのある日 ひとばんのうちに
平和通りが こうえんになった ぼくは
ゆめかと思って ほっぺたをつねってみた
おもわず ヤッホーとかけだした
(中略)
うえきやさんに でんきやさん
たくさんの人たちが 大へんだったろうな
どうもありがとう・・・」
買物公園ができたことは、当時の旭川の小学生にこんなにも感動を覚えさせたのか、ということが伝わる。
買物公園の2015年6月の平日の通行量は12万3千人、土曜日のそれは14万3千人、日曜日は12万5千人である。これは12年前の15万人(平日)、17万6千人(土曜日)、20万7千人(日曜日)と比べると減少してはいるが、近年、多くの中心市街地が衰退化していく中、これだけの集客を未だ誇っていることは評価してもいいと思われる(同じ人口規模の和歌山市で、一時は大阪以南で最大の商店街といわれたぶらくり丁商店街の平均通行量は1992年では5万4千人であったが、2010年には1万7千人にまで落ち込んでいる)。
多くの都市において、モータリゼーションが進展し、郊外に大型商業施設が立地展開している中、旭川市でも同じように中心市街地から人が離れていった。しかし、大型商業施設であるイオンを街中に持ってくるなどして、都心部の商業機能を維持。その結果、同規模の地方中心都市に比べても、街中は賑わいに溢れているし、アーバニティがしっかりと維持されている。そして、そのアーバニティの真ん中にこの買物公園がある。
買物公園が誕生した時、「道路は本来人間のためにある。人のために道を開放する。そして、市民が主体となった街づくりを」という言葉を掲げていたそうである。昨今、海外において新たに整備される人間中心の道路空間が注目を浴びているが、日本の都市にもそれらとの比較に堪える素晴らしい道路空間が昔から存在しているのである。
【取材協力】旭川市役所、旭川平和通商店街振興組合、旭川平和通買物公園企画委員会
「夏休みのある日 ひとばんのうちに
平和通りが こうえんになった ぼくは
ゆめかと思って ほっぺたをつねってみた
おもわず ヤッホーとかけだした
(中略)
うえきやさんに でんきやさん
たくさんの人たちが 大へんだったろうな
どうもありがとう・・・」
買物公園ができたことは、当時の旭川の小学生にこんなにも感動を覚えさせたのか、ということが伝わる。
買物公園の2015年6月の平日の通行量は12万3千人、土曜日のそれは14万3千人、日曜日は12万5千人である。これは12年前の15万人(平日)、17万6千人(土曜日)、20万7千人(日曜日)と比べると減少してはいるが、近年、多くの中心市街地が衰退化していく中、これだけの集客を未だ誇っていることは評価してもいいと思われる(同じ人口規模の和歌山市で、一時は大阪以南で最大の商店街といわれたぶらくり丁商店街の平均通行量は1992年では5万4千人であったが、2010年には1万7千人にまで落ち込んでいる)。
多くの都市において、モータリゼーションが進展し、郊外に大型商業施設が立地展開している中、旭川市でも同じように中心市街地から人が離れていった。しかし、大型商業施設であるイオンを街中に持ってくるなどして、都心部の商業機能を維持。その結果、同規模の地方中心都市に比べても、街中は賑わいに溢れているし、アーバニティがしっかりと維持されている。そして、そのアーバニティの真ん中にこの買物公園がある。
買物公園が誕生した時、「道路は本来人間のためにある。人のために道を開放する。そして、市民が主体となった街づくりを」という言葉を掲げていたそうである。昨今、海外において新たに整備される人間中心の道路空間が注目を浴びているが、日本の都市にもそれらとの比較に堪える素晴らしい道路空間が昔から存在しているのである。
【取材協力】旭川市役所、旭川平和通商店街振興組合、旭川平和通買物公園企画委員会
類似事例
ストロイエ、コペンハーゲン(デンマーク)