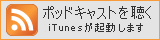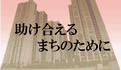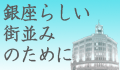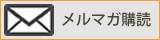まちの価値を維持していくこと 金沢シーサイドタウンに見る「都市デザイン」
編集局 川上正倫
◇1970年代の都市デザインとアーバン・デザインの不幸
金沢シーサイドタウンは、設計者(建築家)の意図がよく反映された事例である。完成したのは1981年のことであるが、計画開始はその10年前に遡る。第一期に槇文彦氏、第二期に大高正人氏、神谷宏治氏、藤本昌也氏、内井昭蔵氏、宮脇檀氏といった建築家たちがプロジェクトに参画している。背景としての設計者の意図を探るため、予備知識的に70年代の建築界を簡単に振り返ってみたいと思う。
当時の日本は、高度経済成長が落着き始め、一世を風靡したメタボリズム(※1)ムーブメントにおいて、大阪万博をひとつの転機に、万博参加建築家たちの活動分化が起こり始めている頃であった。所得倍増計画(1960)や国土総合開発計画(1963)などといった景気をあおる政策が施行され、国が都市拡大に注力する一方、丹下健三氏の「東京計画-1960」をはじめとする建築家の描く都市像は、現実の都市から受け入れてもらえないムードが漂っていた。多くの建築家が個々の建築デザインに集中し始める中、金沢シーサイドタウンに参加した槇氏は、アーバン・デザインへの関わりを継続している建築家であった。建築の拡大としての都市ではなく、建築の集積による都市を思考し、建築によってつくられる「奥」や「すきま」による「見えがくれする都市」を謳っていた。そのアーバン・デザインへの思考を表す成功例として代官山ヒルサイドテラスが挙げられる。しかしながら、ヒルサイドテラスと比較して同時期の金沢シーサイドタウンは必ずしも理想通りにいったわけではないようである。事業を担保していたはずのマスタープランの変更を余儀なくされるなど、固定的な法規による理解欠如をはじめ、社会への対応に終始するなかで独創性を低下させている印象がある。それでもデザインを巡るイニシアティブに関する落胆を上回るアーバン・デザインに対する建築家としての期待が、当時の発言から読み取れる (※2)。ところが、建築家のアーバン・デザインへの期待は、その後82年の中曽根内閣発足とともに訪れたマネーゲームの中で、急激な地価高騰に喘ぐ都市によって70年代以上に受け入れられることはなかった。バブル経済は建築家に対して、より即物的な都市への対応を求め、建築家の興味を都市から完全に奪い去ることで、アーバン・デザインへの挑戦は据え置かれることになり今に至っている。
一方で、田村明氏率いる横浜市が、アーバン・デザイン付きで事業地をつくる可能性を示した金沢シーサイドタウンでの成果は、その後の都市景観行政に大きな進歩を与え、その後の「地区計画」の普及や90年代の幕張ベイタウンのデザインガイドラインへと引き継がれていると考えられる。田村氏はアーバン・デザインとは、「モノとモノ」「モノとヒト」「ヒトとヒト」の3次元を対象とするものであると述べている(※3)。建築家の専門性は本来「モノとモノ」であり、アーバン・デザインにおいてはその領域拡大が望まれる。しかしながら建築家が万能であった中世と異なり、それだけの専門性を要求するには都市は複雑過ぎた。その結果として、建築家を都市から撤退させる一因になった。まずは、アーバン・デザインの三権分立を確立することである。都市をデザインするためのより広範な場の準備を意識しない限り、バランスがとれた「都市」議論が実現されず、「不幸」が繰り返されることが懸念される。
※ 1黒川紀章や菊竹清訓などを中心とした若手建築家、都市計画家によるグループ運動。その名の通り社会変化や人口増加にあわせて有機的に成長していく新陳代謝できる都市や建築の提案を行った。高度経済成長という日本の急速な都市拡張、更新に耐える柔軟性をもつ提案として従来の固定化したル・コルビュジェを中心に展開していたモダニズム形態への批判として盛り上がった。金沢シーサイドタウンプロジェクトに参画している槇氏、大高氏はその中心メンバーであり、その他面々も丹下研究室、菊竹事務所とのつながりから思想的にメタボリズム影響下にあったと考えられる。
※ 2 都市住宅8110「アーバンデザインの今日的課題 対談=槇文彦×林泰義」槇氏は、概念的であったアーバンデザインが横浜市の実践を通して啓蒙期から次の段階へと進んでいるという評価を語っている。
※ 3 田村明 『美しい都市景観をつくるアーバンデザイン』1997年 朝日選書
◇金沢シーサイドタウンにおける街路・街区のデザイン
前置きが長くなってしまったが、建築家の思いは色々あれども、金沢シーサイドタウンは、住民の評価は獲得できているといえる。まず、工業エリアと隣接している住宅地を意識して設けられた緩衝緑地が功を奏している。埋立地における住宅地という印象はまったく感じさせないくらい樹木が生い茂っており、非常に豊かな住空間を形成している。
住宅地に関するアーバン・デザインは、以下のように構想された。
・グリッドパターンの街区割
・通過交通の排除と歩車分離、歩行者専用道路ネットワーク
・個性的な公的建築デザインの導入
・低層住宅ならびに環境配慮の継続
・サイン計画、公園、植樹、ランドスケープも含めたトータルデザイン
ここで意識されているのは、あくまでもアーバン・デザイン付きで事業用地が売却されることである。グリッド街区は、分譲先によらない普遍性の獲得が目的である。歩者分離の道空間は、西欧における広場の概念を日本的に再解釈したものである。日本の風土に適した、低層建築+道の空間によって「領域性」をつくることと、緑に埋もれた建築という「風景」をつくりだすことによって、人々の生活の場として新しい都市に記憶をつくろうと意図されている。現実的には完全な歩者分離は、公共サービスの実現において難しく、ボンエルフの事例参照によって苦労しながら道路行政の理解を得て、現状を実現している。公的建築への建築デザイナーの採用は、表向きは個性的なアクセントを街にもたらすことを目的としている。しかし、他方で分譲先不明の住宅地に対して行政が発注する環境としての質担保が目的と考えることもできる。低層建築の配置として街をデザインしているのも、道空間との関係のほかに、分譲後の変化への環境配慮を促す意図を持っている。
事業体としては、1号地の大部分、2号地北ブロックを日本住宅公団が担っている。前述のように建築としては、1号地については槇氏、2号地については4人の建築家が協同設計している。特にアーバン・デザイン的な観点から横浜市が公団の一律的な団地化を懸念して4人の異なる個性を発揮させようとしている点が興味深い。「アーバン」というのは、文字通り都会という意味である。よって都市には多種多様なデザインがあるべきで、アーバン・デザインとはそれらを共存させ、全体を調和させるものであるべきだという主張である。これも結果としては建築家側の不完全燃焼はあったにせよ、公団の厳しい基準のもとで住民にもわかりやすい良好な住棟、住戸計画となっている。
いわゆる公団仕様と建築デザインの確執やマスタープランの変更など、各建築家間、建築家と事業主体間での調整が、いかに困難であったかは想像に難くない。しかしながら、建築家、事業主体ともに「モノとモノ」「モノとヒト」の専門性なのである。調整役の行政も実は出自を正すと同じ専門であったりする。専門を同じくしてこその相互理解もあろうが、やはりその辺りがオープンな議論といえども「住民」の受動性を高める結果となっているように感じてしまう。ここでの反省は、幕張ベイタウンにどう生かされたのかが、おそらく評価点となろう。金沢シーサイドタウンの価値は、30年以上経った現在からすると、むしろアーバン・デザインによって戦略的に環境継承ができたこと、そしてそれによって改めてアーバン・デザインの重要性を再認識できることであると考える。
建築家の立場からするとアーバン・デザインに携わること自体、職能を発揮する場として発奮することであろう。問題は、その発奮が空回りしてしまうこと、無意識に建築家=万能との勘違いをしてしまうことなのである。金沢シーサイドタウンの経緯を振り返るにあたり、建築家がアーバン・デザインの中でその実力を発揮するためには、モノに対する説得力と提案力によって、厳しい規範や形骸化した常識を上回る構想を抱くことに専念し、あくまで建築の専門性から都市を思い描いているに過ぎぬことを意識して議論に臨むことが重要であると考える。
- 投稿者:東京生活ジャーナル
- 日時:01:09