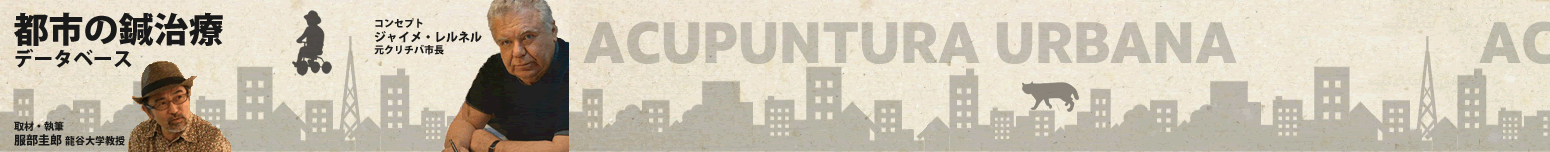ノルウェー第二の都市であるベルゲン。そこには、14世紀頃からハンザ同盟時代のドイツ商人達が住んでいたブリッゲンというカラフルな木造街区がある。他のヨーロッパの都市では木造建築は煉瓦や石造りへと移行していたのだが、ブリッゲンでは同じ材料、そして同じ場所で建物が更新されていった。そして、この木造の建物を作り続けたために、木造という建設材料の制限から、他のヨーロッパの都市のように建物が大きくなることもなかった。これが、ブリッゲンにおいては建築物ではなく、都市空間をも保全されてきた大きな理由である。
ブリッゲンのようなハンザ同盟時代のドイツ商人達が貿易先においてドイツ人街をつくったケースは、ロンドン(イギリス)、ブルッヘ(ベルギー)、ノブゴロド(ロシア)の4つがあるが、当時の状況を最もしっかりと現在に伝えているのはベルゲンのブリッゲンである。ブリッゲンの倉庫群ではたびたび火事が起きたりしていたが、伝統的な技法で修復して使用されてきた。現在の建物の多くは1702年の大火事の後につくられたものであるが、空間的な構造は、12世紀につくられた時のものとほとんど変わっていない。
その街並みを保全させていくうえでの最大の危機は、1955年に起きた火事である。この火事によって、ブリッゲンの北側にあった幾つかの木造建築が焼失した。これを受け、ブリッゲンの他の建物も壊して、この地区を近代化しようという意見が出てきたのである。戦後、世界の多くの都市がモータリゼーションなどに対応して、都市開発などを行っていた時期であり、ベルゲンもその流れに乗るという意見が出てくるのは理解できる。しかし、これに対して、若き考古学者のアスビョルン・ハータイグ(Asbj?rn Herteig)を始めとした市民組織Friends of Bryggen等が強烈な反対運動を展開し、その結果、ブリッゲンは保全されることになった。このブリッゲンが世界遺産に登録されるのは、それから24年しか経っていない1979年である。この登録時期の早さは、それがいかに歴史的価値があるかを示唆しているし、一方で、わずか24年程度で、歴史的街並みの重要性が随分と高まったということも我々に知らしめる。
アスビョルン・ハータイグはベルゲン博物館を設立するうえで大きく貢献し、ベルゲン基金のトップを80歳になる1999年まで務める。彼は、ブリッゲンの保全活動等の功績に対して1970年にナイトの称号を受けたが、その後もブリッゲンの価値を知らしめる著作を幾つか著した。
ブリッゲンが保全されることによって、ベルゲンというノルウェーだけでなく、ヨーロッパの中でも特徴的な物語を有する都市の豊かで複雑な歴史が、それを訪れる人々に分かりやすく、そして驚きを伴いながらも伝えることを可能としている。
ちょっと古いデータであるが2007年のブリッゲンには年間で60万人近くの観光客が訪れた(Innovation Norway)。これは、ノルウェー全体でも4番目に多い集客数であり、改めて振り返ると、これを壊さずに保全した価値の大きさを思い知らされる。
146 ブリッゲンの街並み保全 (ノルウェー王国)







ノルウェー第二の都市であるベルゲン。そこには、14世紀頃からハンザ同盟時代のドイツ商人達が住んでいたブリッゲンというカラフルな木造街区がある。他のヨーロッパの都市では木造建築は煉瓦や石造りへと移行していたのだが、ブリッゲンでは同じ材料、そして同じ場所で建物が更新されていった。
ブリッゲンの街並み保全 の基本情報
- 国/地域
- ノルウェー王国
- 州/県
- ホルダラン県
- 市町村
- ベルゲン市
- 事業主体
- ベルゲン市、Friends of Bryggen
- 事業主体の分類
- 自治体
- デザイナー、プランナー
- N/A、アスビョルン・ハータイグ(Asbjørn Herteig)(保全活動)
- 開業年
- 1702年
ストーリー
地図
都市の鍼治療としてのポイント
ブリッゲンにドイツ商人の手でハンザ同盟の拠点が設置されたのは1360年である。特に沿海で採れる干し魚はヨーロッパ中に輸送され、多くの富をベルゲンにもたらす。この干し魚、そしてヨーロッパ大陸から輸送された穀物は、ブリッゲンの倉庫にて保管された。これらのブリッゲンの倉庫群はある時点では、ヨーロッパ最大の木造建築群であった。その当時、港に入ってくる船からそれを見たものは強烈な印象を受けたであろう。
そして、その強烈な印象は現在、ここを訪れたものにも与える。対岸から観るブリッゲンのカラフルな倉庫群は、北欧の吸い込まれるような青い空と針葉樹林による深緑の山を背景に、まさに一枚の美しい絵のようであり、それが現実の街並みとしては思い難い。なぜなら、都市景観としてはあまりにも非がなく、画家がその豊かな想像力で描いたようだからである。
このような悠久なる歴史、そしてそこで積み重ねられてきた人々の営みがつくりだす景観は、実はベルゲンでなくても美しい。イギリスのランドスケープ・アーキテクトであるジェフリー・ジェリコーが1975年に出版した「The Landscape of Man」という大著がある。ここでは世界中の人の手が入ったランドスケープが描写されているのだが、そこで紹介されている街並みは美しい。特に日本の街並みの美しさは日本人の私をして息を呑むほどのものだが、それらは1950年代から1960年代、つまり50年ちょっと前の街並みなのである。それから50年ちょっと、日本を始めとして世界中の多くの都市が、そのような豊穣なる時間の積み重ねによってつくられてきた街並みを、都市開発、道路整備といった名前のもとに破壊してしまった。そして、それを地元の人々の反対運動や、ちょっとした偶然的な幸運によって保全されたところは、現在、このグローバリゼーションの時代にあって、都市の貴重なアイデンティティを維持している場所として世界的に人々を引き寄せ、また、その歴史が広く知られることで多くの称賛を受け、都市ブランディングとしても成功している。
ブリッゲンの街並みは、それを保全しようとした人々の情熱と努力がその美しさにも反映されていると思われる。多くの本来的な美しさを有する日本の街並みをどう保全するかが課題となっている地域にも多くの示唆を与えてくれる事例であると考えられる。
そして、その強烈な印象は現在、ここを訪れたものにも与える。対岸から観るブリッゲンのカラフルな倉庫群は、北欧の吸い込まれるような青い空と針葉樹林による深緑の山を背景に、まさに一枚の美しい絵のようであり、それが現実の街並みとしては思い難い。なぜなら、都市景観としてはあまりにも非がなく、画家がその豊かな想像力で描いたようだからである。
このような悠久なる歴史、そしてそこで積み重ねられてきた人々の営みがつくりだす景観は、実はベルゲンでなくても美しい。イギリスのランドスケープ・アーキテクトであるジェフリー・ジェリコーが1975年に出版した「The Landscape of Man」という大著がある。ここでは世界中の人の手が入ったランドスケープが描写されているのだが、そこで紹介されている街並みは美しい。特に日本の街並みの美しさは日本人の私をして息を呑むほどのものだが、それらは1950年代から1960年代、つまり50年ちょっと前の街並みなのである。それから50年ちょっと、日本を始めとして世界中の多くの都市が、そのような豊穣なる時間の積み重ねによってつくられてきた街並みを、都市開発、道路整備といった名前のもとに破壊してしまった。そして、それを地元の人々の反対運動や、ちょっとした偶然的な幸運によって保全されたところは、現在、このグローバリゼーションの時代にあって、都市の貴重なアイデンティティを維持している場所として世界的に人々を引き寄せ、また、その歴史が広く知られることで多くの称賛を受け、都市ブランディングとしても成功している。
ブリッゲンの街並みは、それを保全しようとした人々の情熱と努力がその美しさにも反映されていると思われる。多くの本来的な美しさを有する日本の街並みをどう保全するかが課題となっている地域にも多くの示唆を与えてくれる事例であると考えられる。
類似事例
軍艦島、長崎市(長崎県)
ランメルスベルク鉱山、ゴスラー市(ドイツ)
ヴィエリチカ岩塩坑、マウォポルスカ県(ポーランド)
アル・ケ・スナンの王立製塩所、アル・ケ・スナン(フランス)
ランメルスベルク鉱山、ゴスラー市(ドイツ)
ヴィエリチカ岩塩坑、マウォポルスカ県(ポーランド)
アル・ケ・スナンの王立製塩所、アル・ケ・スナン(フランス)