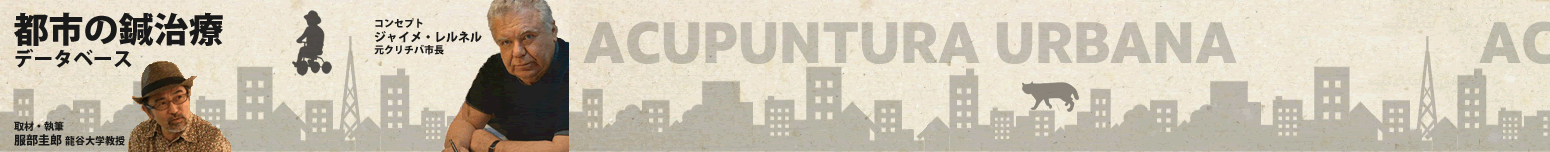台北の国際空港である桃園空港のある桃園県の海岸部にある新屋区は、水稲の産地で「米の都」とも呼ばれている。新屋区だけでも農地は6,000ヘクタールにも及ぶ。日本の占領時代の1939年に、ここには食料の貯蔵を目的とした穀物倉庫と加工工場が建設された。これらの建物は7つあり、すべて煉瓦造りであり、壁は黄土または砂を入れたセメントで塗られた。屋根は日本の瓦でできており、麒麟や獅子などによって飾られている。これらは今日に至るまで、当時のまま保存されている。
この日本の統治時代の建築を修復、保全、再利用するために、当時の行政院客家委員会の羅文嘉委員長は、関連機関の関係者を集め、意見交換をした。2004年のことである。そして、古い穀物倉庫は米博物館として転用し、再利用することが決定された。これは、米食文化に教育と伝承といった新たな役割を付加し、また、この建築物を有効に保全する意義を与えることになった。2007年、この博物館はオープンした。この博物館は、新屋区において営々と続けられた米の生産の歴史や米文化、そしてそれへの重要な貢献をした人工池に対しての展示が為されている。さらに目玉的な展示物として、台湾北部でも珍しい大型の木造精米機が置かれている。
また、館内にはこの米博物館以外にも、農協の生鮮食品を扱うお店や、台湾の農協と漁協の高品質の生産品を展示するスペース、さらにはインフォメーション・センターも設置されている。ここでは来館者はコーヒーを飲んだり、食事ができたりし、また解説員による講義なども開催されたりしている。
稲米故事館は、伝統的な歴史建築物を修復、保全、再利用を通じることで、次世代に歴史文化遺産とその時代の記憶を残そうとしているのである。
(参考資料:台湾文化部の「地方文化館」ホームページ)
071 稲米故事館(台湾)







日本の占領時代に、ここには食料の貯蔵を目的とした穀物倉庫と加工工場が建設された。すべて煉瓦造りで、屋根は日本の瓦でできており、麒麟や獅子などによって飾られている。これらは今日に至るまで、当時のまま保存されている。
稲米故事館の基本情報
- 国/地域
- 台湾
- 州/県
- 桃園県
- 市町村
- 新屋区
- 事業主体
- 桃園県
- 事業主体の分類
- 自治体
- デザイナー、プランナー
- 羅文嘉
- 開業年
- 2007年
ストーリー
地図
都市の鍼治療としてのポイント
台湾は戦前、日本の植民地であった。それらの時期に立てられた建物がいくつか現存している。とりたてて建築価値のある建物であるとは思えないものも多い。しかし、桃園県では積極的に、これらの建物を保全し、日本の植民地というあまり記憶したくない時代であっても、それを次世代に残す記憶装置として、これらの建物を保全する運動が展開している。
これは、その土地にとって、どのような歴史であっても、それはそのアイデンティティの形成に寄与しているという認識があるからだ。
翻って我が国はどうであろうか。自らの価値観にそぐわない建築、記念碑を嫌悪するだけでなく、政治的に中立な建物でさえも、どんどんと取り壊されてしまっている現状がある。その結果、その土地の貴重なアイデンティティを喪失していき、消費社会研究者である三浦展が指摘する「ファスト風土化」が進んでいくのである。それは、人口縮小の時代においては地方の自殺行為とさえいえるような愚行であろう。
台湾は、地方文化を再生するために、いかに地域のアイデンティティを再定義できるかを模索し、多くの施策を展開している。そのうちの重要な施策が、稲米故事館のように、古い建物を保全して次代に継承する試みである。
日本の多くの地方も、長い歴史を有しているところがほとんどである。そして、その歴史を次代に伝えるメディアとして建築ほど適したものはない。稲米故事館のような事例は日本にも多くある。しっかりとそれらを修復、保全し、その地方のアイデンティティを次代に継承すると同時に、人々が共有する記憶装置として活用することを検討すべきであろう。
これは、その土地にとって、どのような歴史であっても、それはそのアイデンティティの形成に寄与しているという認識があるからだ。
翻って我が国はどうであろうか。自らの価値観にそぐわない建築、記念碑を嫌悪するだけでなく、政治的に中立な建物でさえも、どんどんと取り壊されてしまっている現状がある。その結果、その土地の貴重なアイデンティティを喪失していき、消費社会研究者である三浦展が指摘する「ファスト風土化」が進んでいくのである。それは、人口縮小の時代においては地方の自殺行為とさえいえるような愚行であろう。
台湾は、地方文化を再生するために、いかに地域のアイデンティティを再定義できるかを模索し、多くの施策を展開している。そのうちの重要な施策が、稲米故事館のように、古い建物を保全して次代に継承する試みである。
日本の多くの地方も、長い歴史を有しているところがほとんどである。そして、その歴史を次代に伝えるメディアとして建築ほど適したものはない。稲米故事館のような事例は日本にも多くある。しっかりとそれらを修復、保全し、その地方のアイデンティティを次代に継承すると同時に、人々が共有する記憶装置として活用することを検討すべきであろう。
類似事例
新富町文化市場、台北市(台湾)
林百貨店の再生、台南市(台湾)
林百貨店の再生、台南市(台湾)