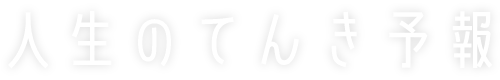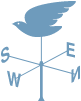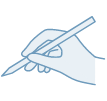高校生の頃は、「ちょっと悪い高校」に進学した中学時代の同級生とよくつるんでいた。といっても、子どものかわいいお遊びのようなもので、警察沙汰になるような悪さはしなかった。
「そうなったら親がうるさいからです。特に母親は過保護なところがあって、少しでも僕の帰りが遅くなると電話をかけてくるんです。友達と一緒のときに母親から電話がかかってくるから、とても恥ずかしかったですね。親への反抗心からわざと家に帰らなかったこともありました」
部活は、中学のときに兄の影響で始めたバスケを高校でも続けていた。ところが、高校2年生のとき、急にバスケをやめてボクシングジムに通い始めた。
「当時、ヤンキーの友達がボクシングをやっていたんです。僕、ヤンキーに憧れていた時期があって、僕もボクシングをやりたいと思ったんですよね。でも、やってみたらあまり好きじゃなかったみたいで、1年で飽きてやめてしまいました」
高校3年生になって大学受験が目前に迫っても、「将来のことは一切考えてなかった」という。地元の近くの大学の経済学部を受験したのは、特にそこで学びたいことがあったからではなく、その大学が公募推薦を受け付けていたからだった。「公募推薦なら秋のうちに結果が出ます。入試を早く終わらせて、高校最後の年を思い切り遊びたかったので、そこを受けました」と高橋さん。父親からは「なぜその大学にしたのか」と厳しく問い詰められたが、「経済を勉強したいから」という理由で押し通した。
「その瞬間が楽しければよかったんです。それに、それまで失敗らしい失敗をしたことがなかったので、『自分はいざとなればやれる』『なんとかなる』という根拠のない自信もありました。だから余計に、将来のことを真面目に考えようとしなかったのかもしれません。将来のことをもっとちゃんと考えていたら、その後の人生も変わっていたでしょうね」
大学生になっても、高校時代の延長にしか感じられず、充実感は得られなかった。「大学生活を面白いと思ったことは一度もありません」と高橋さん。授業にも熱が入らず、20歳になるとお酒を友達と飲み明かす毎日。「飲み会をしたところで何も生まれませんが、その場は楽しいからそれでいい、と思っていました」と高橋さんは話す。