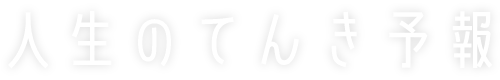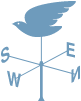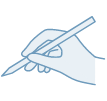研修が終わって営業拠点に配属されると、山本さんは法人営業の担当になった。先輩や同僚に恵まれた職場には刺激があり、また、様々な業種や会社の情報に触れることで社会について学べるのは面白かった。しかし、「アフリカの貧困問題を解決したい」という自分の志と、人の富をいかに増やすかに重点が置かれる銀行の仕事との間に整合性が取れなくなり、次第に息苦しくなっていったという。
私がこの仕事をやる必要あるのかな。
自分の仕事が本当に人のためになっているのか分からずに、自分の個性がどんどん消えてなくなっていく気がして、怖くなった。
その頃、唯一の自己表現は、髪の色を変えたり、派手な格好をしたりすることだった。先輩社員に「お前、何を目指してるんだ?」と注意されるくらい職場では浮いた存在だった。「銀行に染まりたくない気持ちの表れだったと思いますが、自分でもどうすればいいのか分からず、迷走していました」と山本さんは話す。
そうこうするうちに東日本大震災が起きた。東京に住む山本さんに直接の被害はなかったが、「自分もいつ死ぬかわからない」という事実を突きつけられた気がした。「自分にはやりたいことがあるのに、こんなグダグダしていていいのだろうか。先延ばしにするのはもう止めよう」。職場に内緒でアフリカに関連するNGOへの転職活動を始めると、運よく採用が決まった。
ところが、山本さんが退職の意向を上司に伝えても、なかなか承諾されなかった。山本さんを引き留めたい上司は、面談でこうたずねてきた。「山本さんはアフリカに行ったことあるの?」。
山本さんはそれまで、現地を訪れたことは一度もなかった。「ありません」と答えると、上司は山本さんを諭すようにこう言ったのだった。「行ったことがないのに、どうしてアフリカで仕事ができるとわかるんだ?」。
もっと現実を見ろ。上司はそう伝えたかったのかもしれない。しかし、その言葉がかえって山本さんの挑戦意欲をかき立てることになった。