| プログラムへ戻る |
 |
 |
 |
 |
| 第1回 ハイライフセミナー シンポジウム 「複数居住の期待と現状」 各論報告(2) 「多様化する住居形態」 山畑 信博 氏 (東北芸術工科大学大学院芸術工科研究科助教授) |
 |
 |
 |
 |
| ● 背景について
私は、多様化する住居の社会的な背景、所有形態の変化、求められる住居あるいは居室のデザインの変化についてお話ししたいと思います。 |
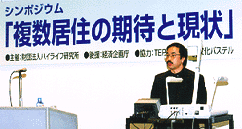
|
|
それからリビングルームですが、最近はフローリングに直接座布団を敷いたりしますし、またかなり低い椅子が開発されており、住宅展示場でも一つのモデルとして提供している場合があります。「座室」といわれる座る生活は、靴を脱ぐことで可能になります。そうした快適性、気候風土、伝統をふまえた様式が、伝統回帰に近いようなかたちで出てきていると思います。 次は高齢者の問題です。実をいうと、今まで住宅計画の研究者の場では、高齢者の問題は論じられていませんでした。しかしここに来て急に、ハード面でバリアフリーにしようとか、もっと進んでユニバーサルデザインにしようといったことや、地方に残した両親の終の住みかをどこに持ってくるのか、自分が帰るのか、あるいは両親を都会に呼ぶのか、そういった問題も出ています。時代は高齢化社会になっていますので、これからモデルを考えるゆとりはないため、試行錯誤的にいろいろなパターンがどんどん出てくると思われます。 新しい集住の形態ということで、先程「コレクティブ」という言葉を使いましたが、スウェーデンの例として、個室があってそこで住むこともできるし、キッチン、ダイニング、寝る場所は各自プライベートとして持っていて保育も可能な、似たような環境の人が集まって集合住宅全体が一つの家族になるようなタイプの住居がアメリカでも急速に普及してきています。日本でも本当に数は少ないのですが、事例はできています。自分ができないことを、それぞれ助け合いながら生活していく住宅といったものが考えられるようになってきていますし、欧米では実際に増えているのです。 それから、展示場やモデルルームに行けば、そこでの生活そのものが何となくイメージされますが、それは自分の生活スタイルと違うのではないか。では、どのようなかたちを求めていくのかという場合、「コーポラティブ」という方法があります。これにはいろいろな方式があって、例えば、ある土地に家を建てたい人を募集します。そこで手を挙げた人が共同で、個々の家族に応じたデザインで集合住宅を造るというものです。地権者がいて、そこのアパートを建て替える場合に募集する場合もありますし、区画整理等で現在の土地を追い出されて別の場所で住むとき、もともと近所付き合いのある人たちが新しく集合住宅を造る場合や、公募型で作っていく場合など、いろいろなタイプがありますが、今後日本で増えていく形態だろうと思います。 |
| ● 所有形態
また、所有の形態についても、従来と違うものがいくつか見えてきています。日本では約6割が持ち家、借家が4割といわれています。戦前の日本では農家の8割が持ち家でしたから、トータルすれば持ち家が多かったのですが、都市部に限って話をしますと、持ち家が3割、借家が7割。特に大阪では、大正15年の借家率は9割と、都心のサラリーマンはほとんど借家に住んでいたわけです。 |
| ● 住宅デザインのこれから
最後に住宅デザインのキーワードを考えると、1990年以降だけに限ってもいろいろな言葉が飛び交っています。まずバリアフリー、これを一歩進めてユニバーサルデザイン、あるいは社会のノーマライゼーション化ということもあります。 |
 |
 |
 |
 |
| このページのTOPへ |